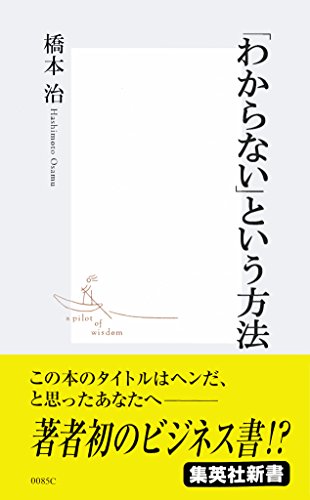まえがき
「自分はどうわからないのか?」──これを自分の頭に問うことだけが、さまざまの「わからない」でできあがっている迷路を歩くための羅針盤である。「自分はどうわからないのか?」それこそが、「わかる」に至るための“方向”である。その“方向”に進むことだけが「わからない」の迷路を切り抜ける「方法」である。「自分はどうわからないのか?」これを自分の頭に問う時、はじめて「わからない」は「方法」となるのである。
第一章 「わからない」は根性である
私のやり方は、結局のところ「わからないからやる」である。これはかなり、自肩のある人間の言うことである。自倍があるのか、バカなのか。普通の場合、これは「わからないけどやる」であり、「わからないけどやらされる」である。
第二章 「わからない」という方法
だから仕方がない、私の「セーターの本」は、そのパカバカしいくらいの「なんにも知らない」を、スタート地点として設定する。それ以外のスタート地点はありえない。業界外の私にとって、それはべつに「恥ずかしいこと」でもなんでもないことだが、「かくあるべきものはかくあるべきもの」という原則が既に確立されている業界内の専門家にとって、それは考えるだに恐ろしい「不可解」なのである。
「納得」に至る道は、くどい道である。なんにも知らない男がセーターを編めるようになるためには、やたらの数の「なにを→どうして」が必要になる。そのプロセスのすべてを、「こうですよ」と図解して教えなければ、身体というものは納得してくれない。つまり、「わかる」へ至るために必要なことは、自分の中に存在して眠っている「わからない」を、すべて掘り起とす作業だということである。
熊川哲也は、世界的に有名な超一流のバレエダンサーである。以前にたまたまテレビを見ていたら、彼の特集をやっていて、そこに子供時代の彼にバレエを教えていた先生が出て来た。/ 北海道でバレエ教室を主宰する女の先生である。この彼女は、子供の頃の熊川哲也が、やたらと「わからない」を連発していたと証言していた。新しいプロセスを彼に教えようとすると、まだ中学生の熊川哲也は、「そんなことできねーよ、先生」と言うのだそうである。口で新しいプロセスを教えられても、「できない、わかんない」を連発して、「じゃ、先生やってみてよ」と言うのだそうである。熊川哲也が「できない」と思うことを先生がやって見せると、首をかしげて、「わかんない」がまた始まるんだそうである。/ バレエダンサーとは、身体を動かすのが商売である。だから先生は、「カクカクシカジカのように身体を動かせ」と言う。しかし言われた方の少年熊川哲也には、その「カクカクシカジカ」がわからない。全体としてそのようになるであろう動きの一々に、自分の身体のパーツがどのように対応しうるかが、口で言われただけではわからないのだろう。だから、実際に先生にやってもらう。目の前に出現した「新しい身体の動き」を見て、「なるほど、カクカクシカジカとはこのようなことか」と理解して、しかし、その動きを自分で再現するとなると、一々の具体的な動きがよくわからない。わからないのは、脳がその動きを概括的に「こうか」と認識しても、その認識が身体各部に対応したものになっていないからだろう。つまり、総論ではわかっても、各論では「わからない」のである。/ 「各論」という身体パーツに十分な理解が及ぶまで、「わからない」は連発される。「各論」の一々を「どうやらこういうものか?」と理解して、そしてその後になって、「総論」としての再構築が始まる。「わからない、わからない」を連発していた少年熊川哲也は、身体各部の動きを「どうやらこういうものらしい」と理解すると、家に帰ってそのことを我が身に実現させるためのレッスンに一人で励んでいたのだという。「前の日に,わからない、わからない”を連発して、しかし少年熊川哲也は、翌日にはちゃんとできるようになっていた」と、彼の先生は往時を語っていた。
もちろん、熊川哲也のすごさは、「次の日にはできるようになっていた」ではない。自分の理解の届かないところを確実に発見して、それに対して「わからない」を明確に確認していたこと──「わからないの掘り起こし」である。
「わかる」とは、自分の外側にあるものを、自分の基準に合わせて、もう一度自分オリジナルな再構成をすることである。普通の場合、「わかる」の数は「わからない」の数よりもずっと少ない。だから「暗記」という促成ノウハウも生まれる。数少ない「わかる」で再構成をする方が、数多い「わからない」を搔き集めて再構成するよりもずっと手っ取り早いからである。手っ取り早くできて、しかしその達成は低い──あるいは、達成へ至らない。「急がば回れ」というのは、いかにも事の本質を働いた言葉で、「効率のよさ」と「効率の悪さ」は、実のところイコールでもあるようなものなのである。
「学ぶ」とは、「師」となった他人の人生と、自分の生き方とを一致させることであり、「わかる」とは、その一致からはずれるような形で存在している「自分自身のあり方」を理解するととなのである。自分と他人の違いは、そのようにある。それは「ある」のが当たり前だから、「学ぶことのうっとうしさ」も、そこから生まれる。/ 「私が学びたいのはあなたの持つノウハウだけです」と言っても、先生となる人は、そんな手前勝手なことを許してくれないからだ。「学ぶ」ということは「生き方を学ぶ」であって、だからこそ、「お行儀」は学習の第一になる。それは、「学ぶ」ということが、「師となった人の生き方を学ぶ」とイコールになっているからである。
だがしかし、この私は「パンク」から編み物を始めた人間である。そんなことを気にしない。「気にしなければならない」という発想が久落している。しかし女というものは、他人の編んだセーターを見る時、まず第一に「編み目が揃っているかどうか」に注目するのである。揃っていれば許す。揃っていなかったら、ケチョンケチョンである。女達の中で編み物を続けるということは、「意地の悪い姑と小姑だけの世界に生息する」と等しいのである。/ そのことに気がついて、私は少し女達が気の毒になった。「編み目が揃う」などということは、ずーっとやってりゃ、その内、自然になんとかなるようなものなのである。セーターの十着も編めば、手が慣れて、「なんでそんなに目が揃ってるの!?」と、女達を驚愕させられるようになる。実際私がそうだった。慣れりゃ実現する程度のことなんだから、そんなことはどうでもいいのである。一番重要なのは、「うるさいことを言わずに手を慣れさせる」で、女の編み物の世界で欠落しているのは、実にこのことなのである。それを知っていたからこそ、私は「編み物業界への挑戦状」を平気で叩きつけられたのである。
話は突然、「教育の崩壊はなぜ起こるのか?」である。既に多くを語る必要はないだろう。多くの女達がなぜ「編み物」から離れてしまったかを考えればいいのである。/ 「学ぶ」とは、教える側の持つ「生き方」の強制なのである。「その生き方がいやだ」と思われてしまったら、その教育は崩壊する。ただそれだけのことである。/ ある時期、「活字離れ」という事態は登場して、それと同じ時期には「編み物離れ」という事態も進行していた。どちらも、「そとにある生き方がいやだ」という嫌悪であり、拒絶である。それが公然となって、しかしそれが拾い上げられずに放置されれば、やがては「教育離れ」という事態へ至る。つまり、「教育の崩壊」である。
ついでだが、私の「セーターの本」の中身は、初級編と上級編と超弩級編の三つに分かれている。「中級編」はない。初級編を何度も繰り返すのがすなわち「中級編」で、「それは、教える側の管轄ではなく、教わる側の管轄だ」と、この私が決めているからである。「中級」とは、初級から上級に至るまでの習熟の期間であって、そんなものは、当人が決めればいいのである。「生き方の強制はいやだからノウハウだけを教えろ」と言える程度の人間に、それくらいの判断力は宿っていて当然のものだからである。その「中級」がなければ、「上級以上」はない。それだけのことである。だから初級編の最後で、私は意地悪なことを言ってしまう――「編み方だけを知ってあなたが編んだセーターは、まだ人前に出せるようなものではない」と。/ それを言うのが教育だと、私は思うばかりである。
第三章 なんにも知らないバカはこんなことをする
仕事が「自分のもの」にならないのは、その仕事の中に隠されている「基本」が見えず、マスターできなくなっているからである。教えられた通りのことを教えられた通りにやっていたって、その先はない。薄っぺらな自分が薄っぺらに見た程度のことだけを「仕事」と勘違いしていたら、すぐに壁にぶつかってしまう。ただそればかりのことである。/ その昔は、「まず基本」がその初めにあった。時代が進むにつれて、「基本」の上に厚い堆積物が積もった。「基本」が見えないまま、小器用な人間がテキトーにやれば、それでOKになった。そして、その二十世紀という便利な時代は、壁にぶつかるのである。「この自分のイージーさはなんかへんだな1」という自覚がない限り、その壁を越えるための「基本」は姿を現さないだろう。それくらいのシビアさはあるのである。
「自分が“わからない”と思うととは、果たして正当なのか、それともトンチンカンなことなのか」と、十分にためらっている。ためらって、その答は出てしまった。だとしたら、その次に来るものは一つー「わからないまんまに突進してみる」である。これを別の言い方にすれば、「自分の直感を肩じる」である。それが肩じるに価するものかどうかを確認して、直感に従って進む。「進める」ということを確認して、その直感の正しさを再検証する。「“わからない”という方法」はこれなのである。
「情報収集」で一番重要な意味を持つのは「記憶」である。ぼんやりと、辺りにあるものを頭の中に囲い込む。ぼんやりとしていればしているほど、この「入り込んで来るもの」の量は多い。普通は、そういうものを「記憶」とは意識しないが、「入ってしまえば記憶」なのである。つまり、情報の収集は無意識を動員してするものなのである。そうして、脳の中になんでも囲い込む。整理とは、その記憶のゴミの山に入り込んで、ゴミの山から、ある道筋に従って、意味のあるものを拾い出す作業である。これをもっと正に言えば、「ゴミの山の中から意味のありそうなパーツを拾い出し、ある道筋に基づいて再構築をする」である。「情報の整理」とは、こういうことなのである。
第四章 知性する身体
この本で私が繰り返し言うことは、「なんでも簡単に“そうか、わかった”と言えるような便利な“正解”はもうない」である。/ これは私にとって、ずっと以前からの「自明の理」のようなもので、その話を始めると私の子供時代にまでさかのぼらなければならないのでやめるが、私が『「わからない」という方法』なる本を書いたところで、それが「これをマスターすればあなたも〇〇ができるようになる」という種類の本にはならないということである。私が言いたいのは、「便利な正解の時代」が終わってしまったら、「わからない」という前提に立って自分なりの方法を模索するしかないという、ただそれだけのことである。「“わからない”という方法」なる言葉自体が、逆立ちした矛盾のようなもので、それはすなわち、「方法はない」なのである。この本を読んだからと言って、「そうか、こうすればいいのか」という理解は起こらない。私は「新しい方法」を提唱しているのではなく、「人の言う方法に頼るべき時代は終わった」と言っているだけなのである。
「わからない」という方法 (集英社新書) | NDLサーチ | 国立国会図書館
914.6